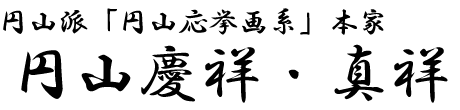円山慶祥 画歴
- 1947年
- 京都市に生まれる(本名 駒池慶子)
- 1954~1960年
- 西川 純に学ぶ <西川 純:浅井 忠に師事し関西美術院に所属>
- 1963年
- 縁戚関係にあたる円山応祥(国井)に師事 <円山応挙第7世 円山応祥:国井応陽に師事し後に山元春挙に学ぶ>
- 1967年
- 京都成安女子短期大学意匠科卒業(ヴィジュアルデザイン科)
- 1981年
- 応祥より「慶祥」の雅号を頂く
- 1981年
- 応祥没す
- 1986年
- 兵庫県香住町 亀居山大乗寺(応挙寺)本堂 位牌堂天井絵 「天舞四季花瑞鳥図」 制作奉納
- 1988年
- 大乗寺本堂 位牌堂 位牌壇地袋 「蓮池図」 制作奉納
- 1994年
- 円山応挙没後200年記念「駒池慶祥展」を開催 (香住町「但馬・理想の都の祭典」主催)
- 1995年
- 京都市東山 都ホテルにおいて「第2回 駒池慶祥展」を開催
- 1999年
- 京都府京都文化博物館において「円山派直系 駒池慶祥・弟子真祥展」を開催(亀居山大乗寺 後援)
- 2000年
- 円山慶祥 襲名
- 2001年
- 京都市勧業館みやこめっせにおいて 雅号命名20周年及び円山襲名披露記念展「円山慶祥・弟子真祥展」を開催
- 2003年
- 京都文化博物館において綾部市塩岳山楞巌寺本堂天井絵「瑠璃光華曼荼羅図」制作披露
「円山慶祥・真祥展」を開催
綾部市塩岳山楞巌寺本堂ならびに天井絵「瑠璃光華曼荼羅図」落慶法要 - 2004年
- 悟真寺信徒として円山応挙の追善菩提の供養を引き受ける
円山応挙の墓について、墓碑銘「源應擧墓」の刻は妙法院宮真仁法親王の筆による - 2005年
- 円山応挙と一門によって描かれた「三井家伝来 圓山派衣裳画」の代表作、『波濤に飛鶴』を亀居山大乗寺(応挙寺)に寄進
- 2007年
- 東京銀座 文藝春秋画廊に於いて「円山慶祥・弟子真祥展」を開催
- 2008年
- 京都文化博物館において「祝 源氏物語千年紀 円山慶祥・弟子真祥」展を開催
- 2009年
- 平成21年1月から平成22年3月末迄
文化女子大学文化ファッション研究機構客員研究員として、きもの制作における円山応挙の役割に関する研究に対する助言を行う。 - 2013年
- 終南山善導院悟眞寺本堂内陣格天井に「極楽浄土寶華図」を制作
- 2017年
- 7月 終南山善導院悟眞寺に襖絵「四季三余図」 23枚 制作・奉納
円山真祥 画歴
- 1971年
- 京都市に生まれる(本名 駒池 真)
- 1991年
- 駒池慶祥に師事
- 1996年
- 嵯峨美術短期大学専攻科 日本画科卒業
- 1997年
- 真祥の雅号を頂く
- 1999年
- 京都府京都文化博物館において「円山派直系 駒池慶祥・弟子真祥展」を開催(亀居山大乗寺 後援)
- 2001年
- 京都市勧業館みやこめっせにおいて 雅号命名20周年及び円山襲名披露記念展「円山慶祥・弟子真祥展」を開催
- 2003年
- 京都文化博物館において綾部市塩岳山楞巌寺本堂天井絵「瑠璃光華曼荼羅図」制作披露
「円山慶祥・真祥展」を開催
綾部市塩岳山楞巌寺本堂ならびに天井絵「瑠璃光華曼荼羅図」落慶法要 - 2004年
- 悟真寺信徒として円山応挙の追善菩提の供養を引き受ける
円山応挙の墓について、墓碑銘「源應擧墓」の刻は妙法院宮真仁法親王の筆による - 2005年
- 円山応挙と一門によって描かれた「三井家伝来 圓山派衣裳画」の代表作、『波濤に飛鶴』を亀居山大乗寺(応挙寺)に寄進
- 2007年
- 東京銀座 文藝春秋画廊に於いて「円山慶祥・弟子真祥展」を開催
- 2008年
- 京都文化博物館において「祝 源氏物語千年紀 円山慶祥・弟子真祥」展を開催
- 2009年
- 平成21年1月から平成22年3月末迄
文化女子大学文化ファッション研究機構客員研究員として、きもの制作における円山応挙の役割に関する研究に対する助言を行う。 - 2013年
- 終南山善導院悟眞寺本堂内陣格天井に「極楽浄土寶華図」を制作
- 2017年
- 7月 終南山善導院悟眞寺に襖絵「四季三余図」 23枚 制作・奉納
円山派直系画系図
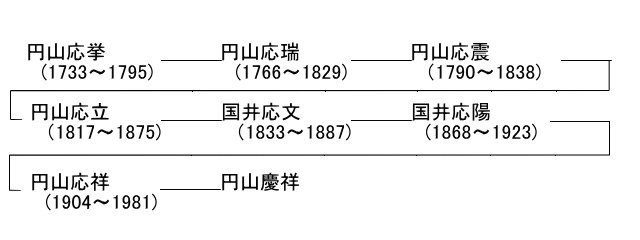
円山応祥先生略記
1904(明治37)年生~1981(昭和56)年没。
本名 国井謙太郎。円山応挙の六世応陽の子として京都に生まれる。
円山派は応挙以後多くの弟子を輩出したが、宗家は応瑞・応震・応立と続いたところで絶え、此の為応瑞の娘であり応震の妹である「やつ」が国井家に嫁いで生まれた国井応文が応立の弟子でもあったので円山五世になり、応陽・応祥と続いた。
応祥は、父応陽に師事し、後山本春挙に学び、1923(大正12)年応陽没後、円山派七世を継ぐ。
1930(昭和5)年 三井家依嘱により英国皇室に額面献上。
1939(昭和14)年 秩父宮、東伏見大妃殿下御前揮毫し御用画拝命。
東京小金井 旧三井家邸の1、2階に襖と障子腰、板戸に応陽、応祥の作品現存。
これらは、京都油小路邸に描かれた作品である。
表千家即中斎宗匠との合作茶掛けを東京美術クラブで展覧し脚光をあびた。
京都左京区の鈴聲山真正極楽寺 真如堂の書院襖に四季花鳥図の応祥作品が現存。
1957(昭和32)年 祇園祭の八幡山鉾に前掛け 綴錦織「平和の鳩」の下絵を制作した。
円山派の絵画鑑定者としても知られた。
享年77歳 川端三条 壇王法林寺に葬られる。
参考資料:東文研アーカイブデータベース 2014 独立行政法人 国立文化財機構 東京文化財研究所
三井家と応挙代々の関係
三井家は江戸時代中期、初代三井高利のころより伊勢の松阪を始めとして江戸・京都・大阪にも両替商・呉服商を営み豪商となる。
円山応挙と三井家との関係は古く数ある三井家十一家の中でも、特に北家(総領家)4代高美(たかはる)最初に応挙と親交を結んだ。
30代半ばで剃髪し隠居後の一成(いちじょう、高美)と親しく交流した応挙は、一成没後の一周忌に「水仙図」を手向けた。
この「水仙図」は、応挙と一成との親交の深さを今に伝えている。
北家5代高清(たかきよ)は、讃岐金比羅宮の書院に費用を負担し、応挙作の襖絵を奉納した。
北家6代高祐(たかすけ)は、応挙・応瑞に絵を学び「平安画家一覧付録」に弟子であったと記されている。
北家10代高棟(たかみね)は、京都北家に出入りしていた国井応文・応陽に絵を学んだ。
高棟は、国井応陽没後、1923年(大正12)応祥を円山派7世相続人として後援した。
応祥は、1935年(昭和10)三井家の神奈川県大磯城山荘竣工式に招かれ、その後、度々訪れて絵を描いている。
参考文献
三井家文化人名録
三井八郎右衛門高棟伝
三井家伝来圓山派衣裳画について
三井家伝来圓山派衣裳画は三井北家10代三井高棟より圓山派7世円山応祥に譲渡された原寸大の小袖の衣裳下絵である。
その後円山応祥から縁戚関係のあった円山慶祥の実母と円山慶祥より亀居山大乗寺に19件を寄進した。
浄土宗終南山善導院悟眞寺について

浄土宗終南山善導院悟眞寺(通称:悟眞寺)は、京都太秦にあり、円山応挙、応瑞、応震、応立、応誠の墓がある事でも知られている。